【1ページ目】2018年7月号 「ドラえもん」-子どものメンタルヘルスに使えるひみつ道具は?
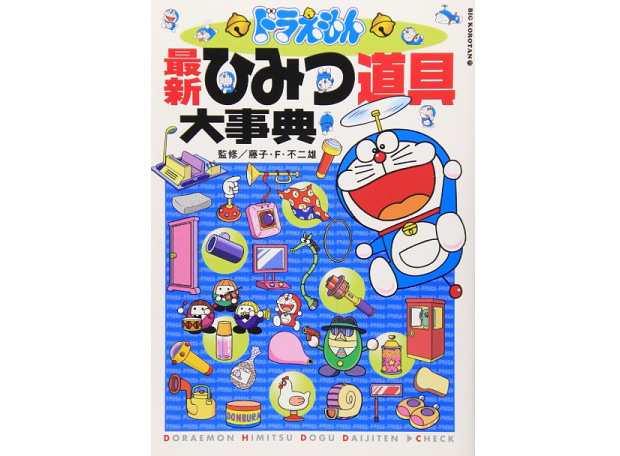 ********
********
・思春期
・好奇心
・反抗
・同調
・認知行動療法
・ブリーフセラピー
********
みなさんは、10代の子どもにどう接して良いか困っていませんか? 例えば、リアクションが薄い、急にキレる、言うことを聞かない、勝手なことをする、友達関係に悩む、そして不登校などです。なぜ彼らは困ったことをするのでしょうか? そもそもなぜ困ったことが「ある」のでしょうか? そして、私たち大人はどうすれば良いでしょうか?
これらの答えを探るために、今回は、まず思春期のメンタルヘルスを、発達心理学的に、比較動物学的に、そして進化心理学的に掘り下げます。そして、子どものメンタルヘルスに使えるドラえもんのひみつ道具を3つご紹介します。と言っても、もちろん本物の道具ではありません。その道具の発想です。これらを使って、思春期の子どもへのより良いかかわり方をいっしょに探っていきましょう。
思春期の子どもはなぜ困ったことをするの?
発達心理学的に考えれば、思春期は、体と同じように、心(脳)も劇的に成長する時期です。そして、自分のことは自分でやる、つまり、自分の行動を自分で決めることができるようになります。まさに子どもから大人になる過渡期です。親から心理的に離れていく、心の独り立ち、つまり心理的自立の時期です(アイデンティティ確立)。
彼らにしてみれば、早く大人になりたい、早く大人と思われたいと思うでしょう。ただ実際には、能力や経験値としては完全な大人ではありません。そのギャップに葛藤が生まれ、困ってしまい、困ったことをしてしまうというわけです。つまり、彼らが困ったことをするのは、彼ら自身が困っているからです。
それでは、ここから困りごとを引き起こす思春期の心理を主に3つあげてみましょう。さらに、私たち人間と同じ社会的動物であるベルベットモンキーというサルの思春期の行動と重ねながら、比較動物学的に掘り下げてみましょう。
①好奇心
1つ目は好奇心です。思春期になると、いろんなこと、特に大人のやっていることに興味を持ち、自分で調べたり、確かめたりするようになります。例えば、それは、セックス、暴力、危険行為、アルコール、ドラッグなどです。それが行き過ぎてしまい、ませて身勝手なことをしているように見えるのです。ベルベットモンキーも同じように、思春期になると、向こう見ずで血気盛んになり、天敵がいるところでも動き回ります。逆に言えば、恐怖心は減っています。
②反抗
2つ目は反抗です。思春期になると、生意気になり、学校の先生をわざと怒らせたりもします。ベルベットモンキーも同じように、思春期になると、わざと親から離れて、天敵に近付いて挑発したりもします。自分の身は自分で守る、「もう大人なんだ」という親へのアピールをします。
③同調
3つ目は同調です。思春期になると、子どもは、親ではなく、同性同年代の仲間といっしょにいようとします。そのために、仲間の行動に合わせようとします。親よりも、友達という社会が大事ということです。逆に言えば、その社会を大事にしないように見える集団の変わり者をのけ者にしようともします。これが、いじめの心理でもあります。ベルベットモンキーも同じように、思春期になると、親からは離れつつ、群れ全体の行動には合わせようとします。
思春期の子どもになぜ困ったことが「ある」の?
これらの3つの思春期の心理は、同性へのマウンティングと異性へのセックスアピールが根底にあることが分かります。つまり、進化心理学的に考えれば、思春期の子どもに困ったことがそもそも「ある」のは、私たちが社会的動物の霊長類になった太古の時代から、生存や生殖に必要だったからであると言えるでしょう。


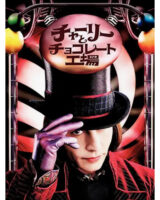
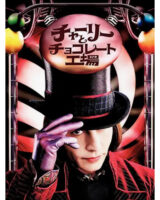

 ページトップへ
ページトップへ