【2ページ目】2025年5月号 記念日「多様な性にYESの日」【その2】だから遺伝しないはずなのに遺伝してるんだ!―同性愛

②兄が多いため?―同種免疫反応
例えば、母親と胎児の血液型が違う場合、母親の免疫系で胎児の血小板への抗体がつくられることがあります。それが胎盤を通して胎児の血小板を攻撃して血小板が減っていく病態(新生児同種免疫性血小板減少症)があります。同じように、母親と胎児の性別が違う、つまり胎児が男性の場合、母親の免疫系で男性特有の物質(H-Y抗原)への抗体がつくられると仮定します(*2)。すると、それがその後に胎盤を通して次の男性胎児(弟)のその抗原を攻撃することが考えられます。そして、その抗原が特に多く分布するのは、男性化するはずの脳であると考えられます。また、この抗体は、母親が男児の妊娠出産を繰り返すたびに増えていくと考えられます。
2つ目は、胎児期の兄への母親の免疫反応が、その後に胎児期の弟に及んで、脳が男性化しにくくなる(同性愛になる)、つまり、同種免疫反応です。
実際の調査(*2)では、兄が多くなればなるほど、確かに同性愛男性の割合が上がっています。なお、姉が多くなるにつれて同性愛女性の割合が上がるわけではない原因については、母親にとって、姉も妹(本人)も同じ女性であり、同種免疫反応が起こりにくいからです。
しかし、これだけでは、女性の同性愛が「ある」原因を説明できません。また、つくられた抗体が攻撃するはずの、男性特有の抗原があるとしたら、それは男性の脳だけでなく男性の性器にもあるはずです。しかし、同性愛男性が不妊になることはありません(*3)。さらに、同種免疫反応が実際にあるとしたら、兄が同性愛なら弟たち全員が同性愛になるはずです。しかし、実際にそうなっているとの調査結果はありません。そもそも、先ほどの新生児同種免疫性血小板減少症は人口の約0.03%(10万人に30人)程度であり、同種免疫反応は頻度がとても低い病態です。
つまり、同性愛の原因は、同種免疫反応で説明するには無理があります。
なお、兄が多くなると同性愛の割合が高くなる、この「兄効果」の原因については、兄が多ければ多いほど、いっしょにいる刺激が性的指向に影響を与えていると指摘する学者はいます(*3)。確かに、その1でもご説明しましたが、性的指向は胎児期に固定化されるとはいえ、性的指向はスペクトラムであることから、完全な異性愛または完全な同性愛ではなく、両性愛を含む中間層は、環境の刺激によって異性愛になるのと同じように、同性愛にもなる可能性は十分に考えられます。
実際に、双子研究(行動遺伝学)において、男性の同性愛への影響度は遺伝22%、家庭環境14%、家庭外環境64%、女性の同性愛への影響度は遺伝37%、家庭環境1%、家庭外環境62%と算出されています(*3)。男性において、家庭環境の違いによる影響度が出ているのは、やはり兄といっしょにいる刺激によるものである可能性が示唆されます。また、家庭外環境の影響が男女ともに60%以上あることから、特に性的欲求が高まる思春期での男子校や女子校、男女別の部活動など同性集団の凝集性が高い環境では同性愛になりやすくなる可能性が示唆されます。しかし、これに関連した調査を行った研究は現時点で見当たりません。参考までに、一時的ながら刑務所で同性愛になる現象(刑務所効果、機会的同性愛)は少なからずみられます。




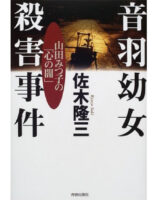
 ページトップへ
ページトップへ