【1ページ目】2025年5月号 記念日「多様な性にYESの日」【その2】だから遺伝しないはずなのに遺伝してるんだ!―同性愛
 ********
********
・包括適応度
・血縁選択
・新生児同種免疫性血小板減少症
・同種免疫反応
・性的拮抗
・性的二型
********
前回(その1)、性の多様性とはどのようなものか、そして、その性が多様であるのはなぜかを進化心理学的に掘り下げました。
 ここで、進化論の視点から、大きな疑問が湧いてきます。同性愛では自分の子どもをつくれない(遺伝しない)わけですが、人口の約3%、例えば学校で30人ちょっとのクラスに1人はいる計算になります。この頻度の高さから、遺伝子の突然変異では説明できません。ちなみに、その1でも登場した、遺伝子の異常であるアンドロゲン不応症や先天性副腎過形成症は、ともに人口の約0.005%(10万人に5人)です。
ここで、進化論の視点から、大きな疑問が湧いてきます。同性愛では自分の子どもをつくれない(遺伝しない)わけですが、人口の約3%、例えば学校で30人ちょっとのクラスに1人はいる計算になります。この頻度の高さから、遺伝子の突然変異では説明できません。ちなみに、その1でも登場した、遺伝子の異常であるアンドロゲン不応症や先天性副腎過形成症は、ともに人口の約0.005%(10万人に5人)です。
それでは、なぜ同性愛はこれほどにも「ある」(遺伝している)のでしょうか?
今回(その2)も、5月17日の「多様な性にYESの日」に合わせて、「記念日セラピー」と称して、この謎に迫ります。
なんで同性愛は「ある」の?
実は、動物の同性愛(同性間の性行動)は、珍しくありません。例えば、人間に最も近い種であるボノボ(チンパンジー)は、特にメス同士が向き合って性器をこすり合わせる「ホカホカ」(G-G rubbing)と呼ばれる行動を頻繁に行います。また、イルカ、ゾウ、コウモリ、テンジクネズミなどでも、それぞれのやり方での同性間の性行動が確認されいます(*1)。
ただし、これらの目的は、あくまで群れの中での同性同士の協力関係や上下関係を確かめ合うためであったり、異性との性行動に向けて練習するためであったり、異性がいない状況での代替行動であったりなどです。人間のように、同性愛のみに限って逆に異性愛を避けているわけではありません。つまり、動物の同性愛は、厳密には両性愛です。そして、あくまで異性愛を主目的とした副次的なものであり、生存と生殖に適応的であることが分かります。
それでは、人間の同性愛はなぜ「ある」のでしょうか? 代表的な3つの説を、進化心理学の視点からいっしょに検討してみましょう。
①親族の子どもを助けるため?-血縁選択
例えば、働きバチや働きアリは、自ら生殖能力を失い、女王バチや女王アリが自分の妹(※母系家族のためオスが生まれるのはもともとごくわずか)をよりたくさん産めるように働き続けます。同じように、人間は、自分が同性愛であることで子どもがつくれない代わりに、親族の子どものサポート役(血縁のヘルパー)になることで、間接的に自分の遺伝子を残している(包括適応度を上げる)と仮定することができます。
1つ目は、同性愛になって親族の子どもを助けるため、つまり血縁選択です。
しかし、実際の調査では、同性愛男性よりも異性愛男性の方が、むしろ兄弟との交流があり、兄弟に対して経済的援助をする傾向があることが分かっています(*2)。よくよく考えると、この説を主張するなら、血縁のヘルパーになるためにわざわざ同性愛になる必要はなく、働きバチや働きアリのように無性愛(性的指向なし)の独身になって親族を助けた方がより間接的に自分の遺伝子を残せます。この状況は、現代ではなく、原始の社会であっても同じです。つまり、同性愛の原因は、血縁選択で説明するには無理があります。
なお、摂食障害については、この血縁選択(包括適応度)が成り立つ可能性が考えられます。この詳細については、以下の記事のページの最後をご覧ください。





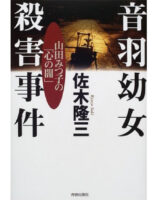
 ページトップへ
ページトップへ