【3ページ目】2025年5月号 記念日「多様な性にYESの日」【その3】逆になんで女性スポーツではNOなの?どうすればいいの?-競技の公平性
新しいカテゴリー分けにすると出てくる新たな問題とは? その解決策は?
 ただし、実際に「テストステロン制限なし」と「テストステロン制限あり」というカテゴリー分けにすることで、新たな問題が出てくることが想定されます。2つ挙げて、その解決策を検討しましょう。
ただし、実際に「テストステロン制限なし」と「テストステロン制限あり」というカテゴリー分けにすることで、新たな問題が出てくることが想定されます。2つ挙げて、その解決策を検討しましょう。
①「逆ドーピング」への取り締まり
1つ目は、「制限あり」のカテゴリーで出場するために、テストステロンを下げる薬を使う男性が出てくることです。テストステロンなどを上げる薬(ドーピング)の逆、つまり「逆ドーピング」です。
この解決策としては、ドーピングだけでなく、この「逆ドーピング」も取り締まりの対象にする必要があります。この点で、トランスジェンダー女性が「制限あり」のカテゴリーで出場する場合、見た目の女性らしくするホルモン療法は、テストステロンを下げる「逆ドーピング」になるため不可になります。一方で、トランスジェンダー男性が「制限なし」のカテゴリーで出場する場合でも、見た目を男性らしくするホルモン療法は、テストステロンを上げるドーピングになるため、当然不可になります。つまり、テストステロンに関係する薬は厳正に取り締まる必要があるわけです。あくまで、その選手本人の持つテストステロンのレベルを重要視するという公正さと一貫性が必要になります。
よくよく考えると、もはや男女で分けないので、「女性として出場する」「男性として出場する」という概念がなくなります。すると、もはや男性らしいか女性らしいかという見た目がどうかよりも、個人個人の身体能力がどうかということに重きが置かれる必要がありますし、そうなっていくでしょう。
②精巣と身体能力の関係への理解
2つ目は、性別適合手術(テストステロンをつくる精巣の除去)をしたトランスジェンダー女性だけでなく、病気(両側の精巣がんなど)や交通事故によって精巣を失った男性も、「制限あり」のカテゴリーで堂々と出場することができるわけですが、それに最初は理解が追い付かない人が出てくることです。
この解決策としては、精巣と身体能力の関係への理解を広げる取り組みをする必要があります。確かに、手術をしても、骨格自体は以前のテストステロンの影響が残ります。しかし、精巣をなくして一定期間を経れば、筋力をはじめとする身体能力はやはり精巣がなくなった(テストステロン濃度が下がった)影響を強く受けます。また、彼らは、競技に有利になるために、精巣をなくしたわけではありません。この点で、彼らが元男性または男性だからというだけで、「制限なし」のカテゴリーにとどめるのは、「男性差別」に当たります。そして、これは、依然として性別二元制にとらわれていることになります。
先ほどと同じように、もはや競技種目を男女で分けないので、「女性として出場する」「男性として出場する」という概念がなくなるため、男性かどうか、元男性かどうかという属性よりも、やはり個人個人の身体能力がどうかということに重きが置かれる必要がありますし、そうなっていくでしょう。
スポーツ競技にも「多様な性にYESの日」が来た時
これまで、男女別にしてきかたらこそ、男女の違いに目が行ってしまっていました。これからは、男女の違いではなく、トランスジェンダーや性分化疾患かどうかでもなく、性別適合手術をしたかどうかでもなく、シンプルに血中テストステロン濃度が基準値以下か以上かだけでカテゴリー分けをして、選手個人個人の身体能力の違いとしてスポーツ競技を楽しむという新しい時代の転換期に来ているのではないでしょうか? そんなスポーツにおいても「多様な性にYESの日」が来た時こそ、再びかつてのように性の多様性をありのままに受け入れ、特別視しない世の中になっているのではないでしょうか?
参考文献
*1 「同性愛の謎」pp.84-88:竹内久美子、文春新書、2012
*2 「LGBTを正しく理解し、適切に対応するために」p.982:精神科治療学、星和書店、2016年8月
*3 「パリ・オリンピック女子ボクシング問題から考える誤解だらけの「性分化疾患」」:谷口恭、医療プレミア、2024
*4 「血液検査用テストステロンキット ケミルミ テストステロンⅡ」(添付文書)p.3:シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、2024




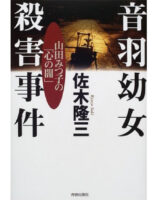
 ページトップへ
ページトップへ