【2ページ目】2019年3月号 映画「八日目の蝉」-なぜ人を好きになれないの? 毒親だったから!? どうすれば良いの?【好きの心理】
なぜ人を好きになれないの?
 恵里菜が人を好きになれないのは、自分はだめで、心を閉ざし、自分が悪いと思っているからということが分かりました。それでは、なぜそうなったのでしょうか? 4歳以降の恵里菜を育てた実の母親の恵津子の心が鍵になります。 ここから、彼女の心理を3つ探ってみましょう。
恵里菜が人を好きになれないのは、自分はだめで、心を閉ざし、自分が悪いと思っているからということが分かりました。それでは、なぜそうなったのでしょうか? 4歳以降の恵里菜を育てた実の母親の恵津子の心が鍵になります。 ここから、彼女の心理を3つ探ってみましょう。
①揺れやすい ―情緒不安定
恵津子は、幼い恵里菜の寝かし付けの時、「日記には本当のことを書きなさい」との絵本の読み聞かせを満面の笑顔でしています。その後に、恵里菜から「お星様の歌を歌って」と言われて歌い出しますが、歌が違うと繰り返し言われてしまいます。すると、恵津子は堪えられなくなり、突然「なんでなの?」と鬼の形相で叫び、泣き崩れます。最後は、恵里菜が「お母さん、ごめんなさい」と連呼するのです。このワンシーンだけを切り取れば、もはやホラー映画です。
1つ目の心理は、心が揺れやすいことです(情緒不安定)。子どもの恵里菜としては、正直に言いなさいと言われて、そう言ったら、怒鳴られたわけです。これは、親の言っていることとやっていることが矛盾しており(ダブルバインド)、子どもを混乱させ、怯えさせます(心理的虐待)。親を求めて近付いていったら、逆に離れていったわけです。すると、子どもとしてみれば、逆説的ですが、親を求めて近付こうとすることをあえて最小限に抑える、つまり心を閉ざすことで、親との距離をある一定範囲内にとどめておこうとします。
これは、何かあった時に逃げ込むべきところであるはずの親自身が、子どもに恐怖を与える張本人でもあるという逆説的で極限的な状況です。例えるなら、親は、もはや守ってくれる安心で安全な基地ではなく、逃れられない恐怖で危険な檻(おり)になっています。これが、恵里菜の自己否定感や不信感を生み出しました。同時に、この恐怖心を植え付けることは、結果的に親が子どもを従わせる無意識の心理戦略になっています(操作性)。
②独りよがり ―条件付きの愛情
恵津子は、戻ってきた4歳の恵里菜がなついてくれず、戸惑います。幼い恵里菜が家出をした時、交番で恵津子は「こんなに心配かけて。どんだけ悪い子なの?」「そんなに、うちが嫌いか?」「そんな悪い子はうちの子じゃないよ」と脅して、突き放します。父親が「いいよ。この子、怖がってる」と止めようとしているのにです。そもそも、恵里菜はその家が嫌だから家出をしたのに、追いかけてきたあげくに「うちの子じゃない」と言われると、混乱してしまいます。また、恵津子は、恵里菜が「そやなくて」「あんな」などの方言を使うと、毎回「それじゃなくて」「あのね」などとすかさず言い直して、直させています。
さらに、大人になった恵里菜が、妊娠4か月であることを恵津子に打ち明けた時、恵津子は即座に「堕ろしなさい。今すぐ一緒に病院に行ってあげる」「そんな子ども育てられるはずないでしょ」「父親もいないのに」と感情的に答えます。「ちゃんと恵里菜の話を聞こう」という父親の言葉かけには耳を傾けません。そして、「私だってね、ちゃんとふつうの母親になりたかったのよ」「恵里菜ちゃんのことをふつうに育てたかったの」と打ちひしがれます。
 2つ目の心理は、独りよがりで押し付けがましいことです(条件付きの愛情)。恵津子は、自分が生後4年間育てていない分、なおさら自分は母親らしくあるべきだ、恵里菜は早く自分の子どもらしくなるべきだというプレッシャーがありました。このプレッシャーは自分を追い詰める同時に、子どもも追い詰めています。子どもの恵里菜としては、言うことを聞かなければ見捨てられると思い込みます。
2つ目の心理は、独りよがりで押し付けがましいことです(条件付きの愛情)。恵津子は、自分が生後4年間育てていない分、なおさら自分は母親らしくあるべきだ、恵里菜は早く自分の子どもらしくなるべきだというプレッシャーがありました。このプレッシャーは自分を追い詰める同時に、子どもも追い詰めています。子どもの恵里菜としては、言うことを聞かなければ見捨てられると思い込みます。
本来、親の愛情は、どんな時もどんなにしていても大切にされ守ってくれる無条件であるはずです。しかし、言うことを聞かない、「ふつう」ではないと急に見捨てられるという条件付きになっています。これは、恵里菜の罪悪感を生み出しました。同時に、この罪悪感を植え付けることも、結果的に親が子どもを従わせる無意識の心理戦略になっています(操作性)。
③ひがみっぽい ―被害者感情
恵津子は、恵里菜に「親だって思ってないくせに。私のこと、苦しめたいんでしょ」「私が親じゃなかったら、こんな目に遭わなかったのにって思ってるんでしょ」と言い放ちます。そして、包丁を恵里菜に向けて、「私が恵里菜ちゃんを大切かどうやって分かってくれるの!?」と迫ります。もはや脅迫です。最後には、「どうすればいいの? 恵里菜ちゃんに好かれたいの」と泣きじゃくります。恵里菜は、「お母さん、ごめんなさい」とまた謝ります。そして、哀れで気の毒になり、母親の手を握り、抱きしめます。もはや、どちらが母親か分からなくなります。
3つ目の心理は、ひがみっぽいことです(被害者感情)。相手の話を聞かず、こんなにしているのにあなたは分かってくれない、ひどいことをするという一方的な自分の視点しかありません。子どもを愛することよりも、子どもから愛されることが第一になっています。
また、恵津子は恵里菜に「(誘拐犯は)世界一、悪い女」と吹き込みます。そして、ものごとがうまく行かないのは「全てあの女のせいだ」という被害者感情に囚われ、すり替えられ、自分の問題点や改善点に目を向けられなくなっています。これが、恵里菜の罪悪感や同情を生み出しました。同時に、この同情を植え付けることも、結果的に親が子どもを従わせる無意識の心理戦略になっています(操作性)。
ちなみに、恵里菜は、大学進学を機に、母親の強い反対を押し切って、一人暮らしを始めます。また、妊娠報告の際には、相手を「お父さんみたいな人」「家庭があって父親にはなってくれない人」と説明します。誘拐犯になった父親の不倫相手は、かつて父親の子を妊娠しますが、中絶して、子どもが産めない体になっていました。その不倫相手に自分を重ねた、とても挑発的な言い回しです。恵里菜には、支配的な母親に対しての抵抗や復讐心もあるようです。


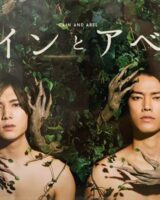
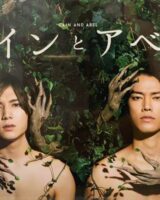

 ページトップへ
ページトップへ