【3ページ目】2019年3月号 映画「八日目の蝉」-なぜ人を好きになれないの? 毒親だったから!? どうすれば良いの?【好きの心理】
なぜ人を好きになるの?
恵里菜が人を好きになれなくなったのは、実の母親の恵津子が揺れやすく、独りよがりで、ひがみっぽいからであることが分かりました。それでは、逆に、なぜ人を好きになるのでしょうか? 4歳以前の恵里菜を誘拐して育てた父親の不倫相手の希和子の心が鍵になります。ここから、彼女の心理を3つ探ってみましょう。

①とにかく守りたい ―信頼感
希和子は、赤ちゃんを見れば不倫をあきらめられると思い、赤ちゃんだけの留守の家に忍び込みました。後の裁判で「あの笑顔に慰められた」「この子を守る」「この子は許してくれている、そう思いました」と語っているように、衝動的に恵里菜を誘拐しました。そして、恵里菜に「薫」という中絶しなければ本来生まれるはずだった子どもの名前を新しく付けます。
希和子は、薫(恵里菜、以下略)とともに逃避行を続ける中、「薫といっしょにおれますように。明日も明後日もその次も。どうかどうかいっしょにおれますように」と祈ります。
1つ目の心理は、とにかく守りたいことです(信頼感)。守るためにただいっしょにいたいという気持ちから、希和子は薫の存在をそのまま丸ごと受け止めています。薫にとって、安心で安全な基地になっています。
対照的に、恵津子は、いっしょにいないことが多く、突き放すこともあり、恵里菜をそのまま受け止めてはおらず、決して守ってはいませんでした。
②全部あげる ―無条件の愛情
希和子は、3歳の薫に「いろんとこ行こう。いろんなものをママといっしょに見よう。きれいなもの全部。ママ、働くよ」と伝えます。その後、薫が4歳になり、警察の捜査が間近に迫っていることを悟った希和子は、写真館に行き、薫との記念写真を撮ります。そして、「薫、ありがとう。ママは薫といっしょで幸せだった」と言い、両手を合わせて膨らませて、何かを上げるしぐさをします。「なあに?」ときょとんとする薫に希和子は「ママはもういらない。何にもいらない。薫が全部持って行って。大好きよ」と言い残します。
2つ目の心理は、全部あげることです(無条件の愛情)。「全部持って行って」という言い回しは、裏を返せば、「もうあげられない」という無念さも込められています。それくらい希和子は薫に自分のできる全て、自分の全部をあげたかったのでした。いろいろ見せて、どきどきわくわくする思い出をいっしょに積み重ねたかったのでした。希和子の愛情は無条件です。
対照的に、恵津子は、家族のイベントを全くしておらず、恵里菜に本当に大事なものはほとんど見せず、ほとんどあげていませんでした。
③ただ幸せを願う ―コミットメント
希和子は、最後に逮捕された時、薫を保護する女性刑事に「その子はまだご飯を食べていません。よろしくお願いします」と叫びます。後の裁判の時、希和子は「4年間、子育てをする喜びを味わわせてもらったことを秋山さん(恵津子)夫妻に感謝します」「お詫びの言葉もありません」と述べます。そして、懲役6年の刑で出所してから、薫との記念写真をわざわざ取りに行っています。
3つ目の心理は、ただ幸せを願うことです(コミットメント)。逮捕された時、自分の身よりも、薫がお腹をすかせていることがまず気になるくらい、薫のことを一番に考えています。そして、その気持ちは、裁判の時も、出所してからもずっと変わりません。お詫びをはっきり言わなかったのは、薫といっしょにいた4年間はかけがえのない意味のあるものだったと確信しているからでしょう。もう一度人生をやり直すとしても、同じことをすると確信しているからでしょう。そこには、法律的な善し悪しは別にして、信念(コミットメント)があります。はっきりお詫びをしてしまったら、それが間違いだったと認めることになります。
原作では、薫との4年間の思い出を心のよりどころにして、希和子が生き続ける様子が描かれています。かつて子どもの産めない体になった希和子は、恵津子から「がらんどう」と言われました。その後の希和子は、もはや決して「がらんどう」ではないことが分かります。その4年間が希和子の生きた証になったのでした。
対照的に、恵津子は、自分の思い通りになるという自分の幸せを第一にしてしまい、恵里菜の幸せを第一にしていませんでした。


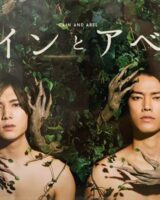
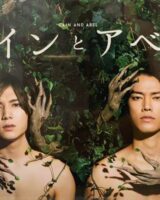

 ページトップへ
ページトップへ