【1ページ目】2025年9月号 アメリカドラマ「24」シーズン1エピソード16【その2】なんで腰抜けや記憶喪失は「ある」の?-進化精神医学から迫る解離症の起源
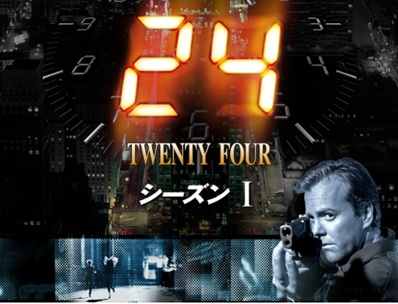 ********
********
・迷走神経反射
・解離性健忘
・脱力発作
・離人感・現実感消失症
・解離性神経学的症状症
・解離性遁走
********
前回(その1)、失神するメカニズムから、腰抜けや記憶喪失になるメカニズムを、脳科学の視点から仮説を使って解き明かしました。
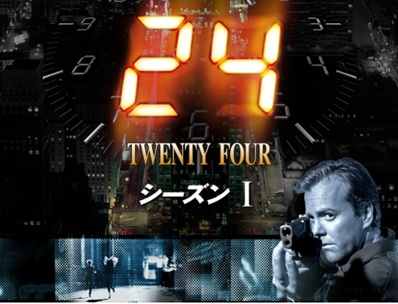
>>【その1】なんでショックで記憶喪失になるの?
なんで恐怖で腰が抜けるの?-脳科学から解き明かす解離性健忘のメカニズム
このシネマセラピーの記事では、これまでほぼすべての精神障害の起源を掘り下げてきました。これらの現象も、その起源がありそうです。それでは、そもそもなぜ迷走神経反射、腰抜け、そして記憶喪失は「ある」のでしょうか?
この謎の答えに迫るために、今回も引き続き、アメリカドラマ「24(トゥエンティ・フォー)」を踏まえて、進化精神医学の視点から、これらの病態の起源に迫ります。
なお、正式名称としては、記憶喪失は解離性健忘、腰抜けは脱力発作です。ただ、この記事では、分かりやすさを優先して、よく使われる通称の「腰抜け」「記憶喪失」で表記します。
じゃあなんで迷走神経反射、腰抜け、そして記憶喪失は「ある」の?
迷走神経反射、腰抜け、そして記憶喪失の病態のメカニズムが分かりました。それでは、そもそもなぜこのような病態は「ある」のでしょうか?
ここで、進化医学の視点から、進化の3つの時期に注目して、これらの病態の起源を掘り下げてみましょう。

①死んだふりで生き延びる―迷走神経反射の起源
約5億年前に魚類が誕生してから、天敵が近くにいる時に危険を素早く察知する扁桃体が進化しました。同時に、天敵に追い詰められて戦うことも逃げることもできなくなった時にいったん動かなくなる迷走神経反射も進化しました。これは、その間に天敵を油断させて、また動けるようになったら、すきを見て逃げるための、捨て身の生存戦略です。
1つ目の進化は、死んだふり(擬死)で生き延びることです。実際に、現在、迷走神経反射に類似する現象は、魚類から、両生類、爬虫類、鳥類、そして哺乳類まで多くの動物で確認されています(*5)。たとえば、「タヌキ寝入り」は日常的な言い回しになるくらい有名です。
これが、「戦うか逃げるか、または固まるか(”fight, flight, or freeze”)」と呼ばれるゆえんです。そして、これが、迷走神経反射の起源であり、五感や体感の感度が鈍くなり、現実感がなくなる病態(離人感・現実感消失症)の起源でもあります。
つまり、迷走神経反射は、太古の私たちの祖先が獲得した進化の産物の名残りだったというわけです。だから、迷走神経反射は「ある」のです。
②困ったふりで生き延びる―腰抜けの起源
約700万年前に人類が誕生して、約300万年前にアフリカの森からサバンナに出て、血縁で集団になって助け合う社会脳が進化しました。そんななか、天敵である猛獣から逃げきれない絶体絶命な状況になった時、先ほどの死んだふりではなく腰が抜けるだけで意識がある方が、いっしょにいる仲間たちに運んでもらい、逃げるのを助けてもらえるチャンスは増えるでしょう。これは、仲間頼みの捨て身の生存戦略です。
2つ目は、困ったふりで生き延びることです。「ふり」という言い回しをあえて使っていますが、先ほどの「死んだふり」と同じように、もちろん本人が意識してできることではなく、無意識です。
これを支持する事実が2つあります。1つは、性差です。実際に、腰抜けを含む解離性神経学的症状症の性差においては、男性よりも女性が2~3倍多いです(*1)。これは、腰抜けになることによって、女性は周りの体格で勝る男性たちから援助行動を引き出すことができます。一方で、その逆の男性が腰抜けになる状況は、体格差から考えると、負担が大きいため、助けてもらえる可能性が低くなります。この点で、現代でも、「腰抜け」という言葉は、女性ではなく、男性に対しての軽蔑の言葉になっていることも納得が行きます。このような事情によって、腰抜けになる人が特に女性で増えるような進化の選択圧がかかり、性差に表れていると言えるでしょう。
もう1つは、腰抜けになるのは人間だけであるという事実です。人間以外の他の動物で明らかな腰抜けは確認されていないことからも、腰抜けは、動物で唯一助け合いをする人間ならではの現象であると言えるでしょう。なお、ペットの犬や猫が獣医から「腰が抜ける」と指摘されることはあります。しかし、その原因のほとんどは、心理的なもの(重度ストレス)ではなく、ビタミン不足や外傷などの身体的なものであると言われています。


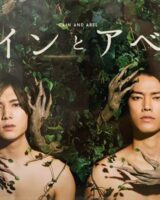
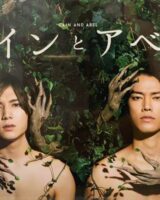

 ページトップへ
ページトップへ