【2ページ目】2013年11月号 ドラマ「Mother」【前編】過剰適応
虐待を受ける怜南はどんな子?
このような虐待を受ける怜南は、どんな子でしょうか? 怜南は、他の子と違い、クラスの中で浮いた存在です。しかし、まだ小学1年生なのに、大人に対してはとても「良い子」なのです。その特徴を3つのポイントで挙げてみましょう。
①観察力
1つ目は、怜南はよく見ており、よく気が付くことです(観察力)。慣れない教職のストレスによる奈緒の円形脱毛に奈緒よりも誰よりも早く気付き、帽子をプレゼントします。後に、うっかりさん(奈緒の実母)に出会った時も、うっかりさんが外し忘れたクリーニングのタグをすぐに見つけます。
②過剰適応
2つ目は、周りの気持ちを見透かし、物分りが良すぎることです(過剰適応)。怜南は、母親に自分の大切な本を勝手に捨てられても、「いらない」と言います。ペットのハムスターが天国に行ったと言われたら、すぐにそれを受け入れ、何事もなかったようにしています。母親の恋人にゴミ袋に閉じ込められても、「かくれんぼしてたら、出られなくなっちゃって」と母親に笑顔を浮かべます。
そして、奈緒には、「(ママのこと)大好き。決まってるでしょ」「ホッとした?」と母親をかばいます。その後に、奈緒と逃げていて行き場を失った時には、「置いてって」「先生、我慢しなくていいよ」と申し出ています。また、奈緒の東京の実家で、育ての親や兄弟に事態がばれて揉めている時は、奈緒に「お母さんになってくれたのありがとう」「お母さんずっと大好き」と置き手紙を残し、一人で北海道に帰ろうとします。奈緒が「あの子はウソでしか本当のことが言えないの」と言います。怒ったり、弱音を吐いたり、甘えたりすることが決してないのです。
③演技性
3つ目は、相手の懐にすぐに入り、気に入られること、取り入ることに長けています(演技性)。どんな人でも、初対面で好印象を与え、すでに大人と渡り合っているのです。怜南が奈緒に「先生って面白いね」「怒った?」「私のこと嫌いなのかな?」と言い、奈緒と距離を縮めるシーンが分かりやすいです。この時、怜南は、自分と同じように生きることに満たされていない奈緒に、親しみを感じていたのでした。
怜南はなぜ「良い子」なのか?
このように、怜南は、よく気が利き、物分りが良く、すぐに好かれる「良い子」なのです。これは、たまたま怜南がこういう性格だったのでしょうか? 違います。怜南は、「良い子」になってしまう必然的な理由があったのです。それが、虐待です。奈緒の同僚の教師が「頼れる者が親しかいないからです」と説明しています。
怜南の母親の回想シーンで明かされたのは、虐待が始まった当初、怜南が必死になって母親の顔色をうかがっていることです。怜南の母親は、早くに夫に先立たれ、一人で仕事と育児を両立させ、心に余裕がありません。一生懸命にやっているのに、育児は思い通りには行かず、その欲求不満の矛先が、弱くて幼い怜南に向けられてしまったのです(「育児ノイローゼ」)。
例えば、不機嫌な母親に怜南が「ママ、がんばって」と励ますと、母親は、「うるさい!」と突き飛ばします。しかし、その後すぐに、びっくりした顔の怜南を見てやりすぎたと思い、「ぎゅっとしよ」と言い、抱きかかえます。人は完璧ではないので、どんな家庭でも、時に親は子どもにそのような対応をしてしまうことがあるでしょう。しかし、これがずっと続いていたらどうでしょうか? 母親は本来、どんな時も子どもにとって安心感や安全感が得られる「安全基地」であるはずです(無条件の愛情)。しかし、母親がこのように情緒不安定だと、今は機嫌の良い母親なのか機嫌の悪い母親なのかと子どもは混乱します。抱き付いた方が良いのか、それとも逃げた方が良いのかという二重の気持ちに縛られてしまいます(ダブルバインド)。
また、怜南が母親に海に連れて行ってもらい、楽しく遊んでいる時のことです。怜南が貝殻遊びに夢中になっている隙に、母親は耐えられなくなって、突然、置き去りにします。しかし、怜南は、いつのまにか母親に追い着き、肩で息をしています。怜南は、すでに見捨てられるということを察知していて(見捨てられ不安)、母親の顔や様子に敏感なのでした(観察力)。そして、興味深いのが、その直後に「ランラ、ランラ、ランラン♪~」と母親の後ろで鼻歌を歌うことです。怜南は鼻歌を歌うくらい楽しい気分だったのでしょうか? 違います。この母親に見捨てられまい、気に入られようとして、必死に取り繕い(演技性)、取り入っているのでした(過剰適応)。
このような過酷な環境の中で生き残るために見出されたのが、この「良い子」という心理です。これは、常に母親の顔色や言動を伺っている中で際立って発達してしまった能力です。ちょうど視覚障害者の聴覚が敏感になるように、虐待という環境に適応するための能力を過剰に発達させてしまったのです(代償性過剰発達)。一方、怜南のクラスメートたちは、普通の家庭で育っているため、このような発達は起きず、無邪気なままです。


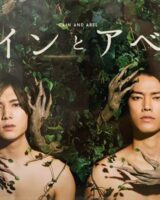
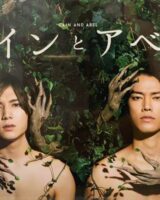

 ページトップへ
ページトップへ