【3ページ目】2025年3月号 ドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会~」【その3】だから子どもの自己肯定感も自殺率も世界最悪なんだ!じゃあどうすればいいの?―「ブラック教育文化」
新しい「日本人のつくり方」とは?
ラストシーンで、その1で登場した1年生の女子は、音楽会の本番に臨む直前、他のメンバーから「私たちは心臓のかけらで、みんなが揃ったらこんな形(両手でハート形をつくる)になる。で、1人こんなふうにずれたら、もう心臓はできない」と言われて、「私たちは過酷な楽器だよ」という名言を残します。まさに従来の「日本人」がつくられる瞬間を見ているようでした。微笑ましく見える一方で、やはり危うさもはらんでいます。それだけに、彼女の将来の行方も気になります。
この映画は、「外国から見た日本の小学校とは」という視点で、海外の関係者や私たちに改めて学校教育のあり方を考えさせてくれました。それは、 海外の学校としてはまだやり足りないと気づかされ、日本の学校としてはもうやりすぎだと気づかされるというギャップです。
 この映画をきっかけに、私たち一人ひとりが学校教育のあり方について情報発信をどんどんしていけば、小学校をより良くしようという社会的なムーブメントを起こせるはずです。その時こそ、新しい「日本人のつくり方」が見えてくるでしょう。それは、生徒たちそして先生たちが、日本人の本来の良さである規律、協調性、忍耐力を保ちつつ、同時に不安や受け身にならず、もっと学校を楽しみ、もっと自分の学び方そして生き方を選ぶことです。それは、映画で先生たちが繰り返し強調していた「自分らしさ」(アイデンティティ)と「自主性」(勤勉性)を真の意味で育むことでしょう。
この映画をきっかけに、私たち一人ひとりが学校教育のあり方について情報発信をどんどんしていけば、小学校をより良くしようという社会的なムーブメントを起こせるはずです。その時こそ、新しい「日本人のつくり方」が見えてくるでしょう。それは、生徒たちそして先生たちが、日本人の本来の良さである規律、協調性、忍耐力を保ちつつ、同時に不安や受け身にならず、もっと学校を楽しみ、もっと自分の学び方そして生き方を選ぶことです。それは、映画で先生たちが繰り返し強調していた「自分らしさ」(アイデンティティ)と「自主性」(勤勉性)を真の意味で育むことでしょう。
なお、今回は、小学校の教育改革についてまとめました。中学校の教育改革については、以下の記事をご覧ください。
参考文献
*1 「高校生の生活と意識に関する調査」における国際比較、文部科学省、2017
*2 こどもの自殺の状況と対策p.54:厚生労働省、2024
*3 小学校段階における同調圧力に対する自己肯定感の影響と居場所感について:松井柚子・高平小百合、日本教育心理学会、2020



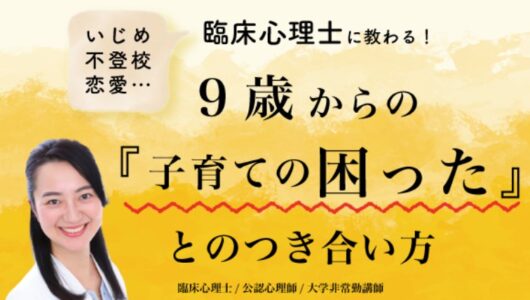
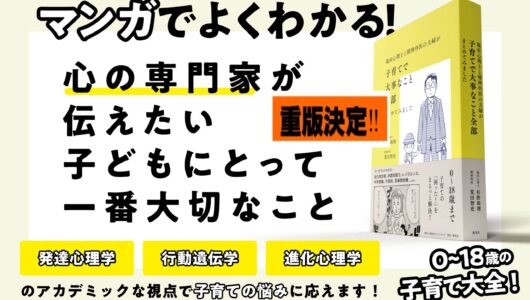




 ページトップへ
ページトップへ