【1ページ目】2025年3月号 ドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会~」【その3】だから子どもの自己肯定感も自殺率も世界最悪なんだ!じゃあどうすればいいの?―「ブラック教育文化」
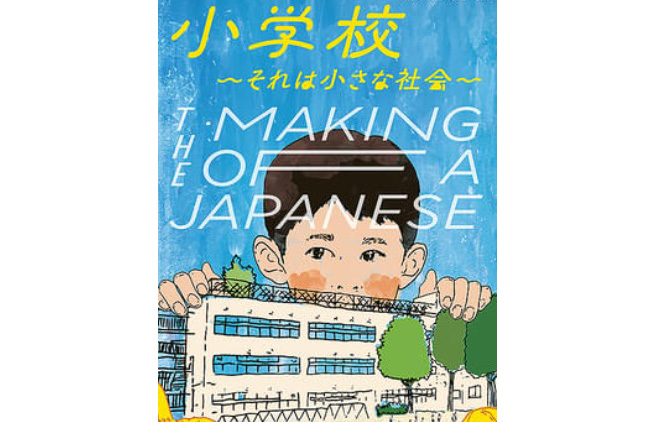 ********
********
・学習指導要領
・同年齢同学年(学級固定化)
・教育の平等
・教育の公平
・人権意識
・異年齢教育
********
前回(その2)、ドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会~」のいくつかのシーンを通して、同調圧力、モラルハラスメント、スケープゴートがはびこる学校での生徒と教師のそれぞれの心理を解き明かしました。
このような日本の学校教育の危うさを踏まえると、実はこの映画は、日本の社会問題でもある、以下の3つの現象の謎を解くための大きなヒントになりそうです。
・不登校の生徒数が過去最多を更新し続ける現象
・子どもの自己肯定感が世界で最低レベルである現象(*1)
・子どもの自殺率が世界でトップレベルである現象(*2)
今回(その2)、引き続きこの映画のいくつかのシーンを通して、教師たちも不安で受け身になってしまった原因に迫ります。それを踏まえて、これからの子どもが学校を楽しむ、そして人生を楽しんでいくためにどう学校制度を改革すればいいのかをいっしょに考えていきましょう。
なお、この映画はドキュメンタリーであり、実在する人物が登場していますが、この記事で教師個人を批判する意図はまったくありません。あくまでその教師たちすら巻き込む文化としての日本の学校教育の危うさを批判しています。
そもそもなんで先生も不安で受け身になってしまったの?―「ブラック教育文化
あるさりげないワンカットでは、1年生の子どもたちが自分の大きなランドセルを棚に無理やり押し込もうとする様子が映し出されます。彼らがこれから画一的な学校教育という枠組みに無理やり押し込まれる姿に重なり、痛烈な皮肉のように見えてしまいます。そして、先生たちもまたその枠組みに押し込まれていたのでした。
教師たちの心理は、生徒たちと同じように、やることが多すぎて実は不安で楽しめない、やることを変えられなくて実は受け身で選べないということが分かりました。それでは、なぜ生徒たちだけでなく、教師もそうなってしまっているのでしょうか?
そのわけは、戦後に学力の地域差をなくすという「教育の平等」の名のもと、学習指導要領、検定教科書、同年齢同学年(学級固定化)の教育政策が徹底されたからです。そして、教師が生徒を高度に管理するようになったからです。しかし、同時にそれは、教師も教師同士で管理される側になってしまったのでした。昭和までは、学校で生徒をコントロールするため、教師による体罰をはじめとしてさまざまな懲戒権が当たり前のように行使され、社会で受け入れられていました。そして、この記事で何度も登場する同調圧力、モラルハラスメント、スケープゴートも学校教育として根付いていったのでした。これを名付けるなら、「ブラック教育文化」です。このネーミングは、ブラック校則にちなんでいるわけですが、実は、日本の学校にはただ「ブラック校則」があるのでなく、その根っことなる「ブラック教育文化」が潜んでいたと言えます。
しかし、時代は変わりました。令和では、情報化とあいまって個人主義の価値観が完全に広がり、人権意識が高まりました。映画では、ある先生が「(クラス全員が)チームとして一体になれ」と力説していましたが、もはや令和の社会ではそうする必要も、そうする価値も置かれなくなりました。そうしたい人だけがそうすればいいだけで、そうしたくない人を巻き込む(強制する)のは、やってはいけないことと認識されるようになったのです。こうして、ようやく人権意識が世界基準に追い付いたのです。
この変化によって、体罰だけでなく、同調圧力、モラルハラスメント、スケープゴートを使うという手段も、社会ではアウトになりました。例えば、学習塾、習いごと、スポーツチームなどでは、ビジネスだけに人権意識には敏感です。テレビやネットでも、人権侵害の話題はすぐにニュースになります。近所の人から怒鳴られるようなことがあれば、すぐに警察に通報するご時世です。家庭でも、少子化であることもあり、子どもは大切にされています。ところが学校に限り、指導という建前のもと、少なくとも教師たちは同調圧力、モラルハラスメント、スケープゴートの手段はセーフだと思い込んでいるのでした。そして、その事実が、この映画で世界に発信され、明るみになってしまいました。
 これは、人権意識が、学校外(社会)では高まっているのに学校内では高まっていないというギャップがあるという現実です。そのギャップが開けば開くほど、子どもは学校に行きたがらなくなり、自己肯定感が下がり、そして自殺率が増えていくわけです。これが、この記事の冒頭で触れた謎の答えです。逆に、昭和までは体罰などのもっと激しい人権侵害があったのに、このギャップがなかったことで、それが「当たり前」のように受け止められました。そのため、不登校は目立たず、子どもの自己肯定感は問題にされず、子どもの自殺率は低かったのでした。
これは、人権意識が、学校外(社会)では高まっているのに学校内では高まっていないというギャップがあるという現実です。そのギャップが開けば開くほど、子どもは学校に行きたがらなくなり、自己肯定感が下がり、そして自殺率が増えていくわけです。これが、この記事の冒頭で触れた謎の答えです。逆に、昭和までは体罰などのもっと激しい人権侵害があったのに、このギャップがなかったことで、それが「当たり前」のように受け止められました。そのため、不登校は目立たず、子どもの自己肯定感は問題にされず、子どもの自殺率は低かったのでした。
簡単に言えば、学校の外と比べて、相対的に中での自分の人権が尊重されていないために、それらの手段が「当たり前」ではなく「異常であり苦痛である」と認識するようになったのでした。これは、同僚、友人、知人などの身近な周りの人たちと比べて、自分が経済的、人間関係的に恵まれていないと不満を抱く心理(相対的貧困、相対的剥奪)と似ています。実際の研究では、令和の時代において、小学校での同調圧力が高ければ高いほど、自己肯定感は低下することが分かっています(*3)。
なお、文化進化の視点から見た学校(学歴社会)の歴史の詳細については、以下の記事をご覧ください。
また、生徒や教師が受け身である原因は、「ブラック教育文化」だけでなく、さらにその根っこには日本人ならではの「直系家族の文化」の影響が考えられます。この詳細については、以下の記事をご覧ください。


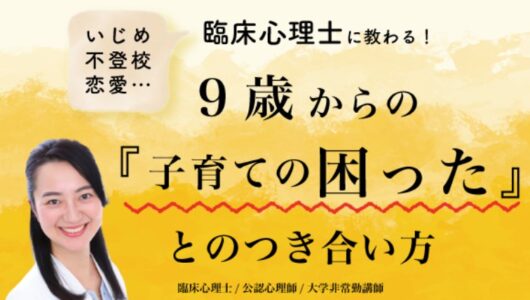
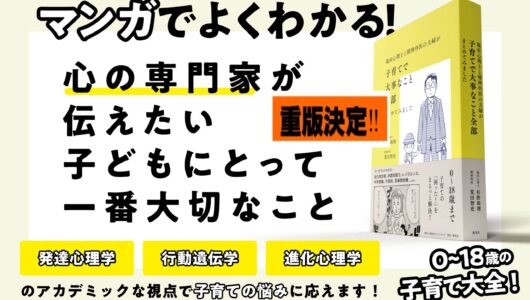


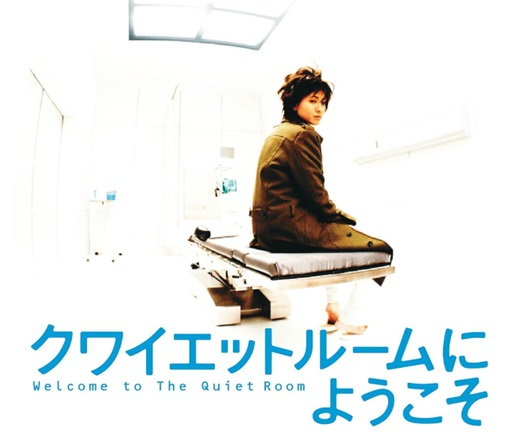



 ページトップへ
ページトップへ