【1ページ目】2025年11月号 映画「エクソシスト」【その2】だから憑依は「ある」んだ!-進化精神医学から迫る憑依トランス症の起源
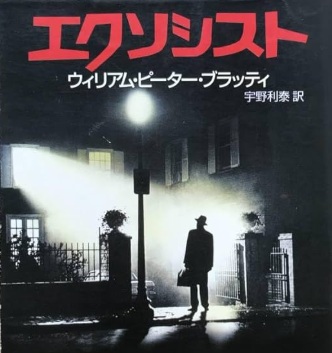 ********
********
・演技性
・退行
・同調性
・ストックホルム症候群
・被暗示性
・祈祷性精神病
********
前回(その1)、憑依するメカニズムを、脳科学の視点から仮説を使って解き明かしました。
しかし、暗示の影響程度で特定のニューラルネットワークが分離する根本的な原因については説明していませんでした。つまり、そもそもなぜ憑依は「ある」のかと言うことです。
この謎の答えに迫るために、今回も引き続き、映画「エクソシスト」を踏まえて、進化精神医学の視点から、憑依の起源に迫ります。
なお、憑依の正式名称は憑依トランス症です。ただ、この記事では、分かりやすさを優先して、そのまま「憑依」で表記します。
なんで憑依は「ある」の?
ここで、進化精神医学の視点から、3つの心理の進化に注目して、憑依の起源を掘り下げてみましょう。
①演じる心理-演技性
約700万年前に人類が誕生し、約300万年前に部族集団をつくるようになりました。まだ言葉を話せないなか、けがをして動けないから運んでほしいことなどを何とか身振り手振りや表情などの非言語的コミュニケーションで演じて伝えていたでしょう。そして、大げさに演じた方が、より助けてもらえたでしょう。
1つ目は、演じる心理、演技性です。これは、相手にどう見られるかを想像する能力(心の理論)によって、「困ったふり」で生き延びることです。なお、演じる心理の起源の詳細については、以下の記事をご覧ください。
この「困ったふり」を無意識に演じるように進化した心理現象としては、いわゆる「幼児返り」「赤ちゃん返り」(退行)、そして拘禁反応(ガンザー症候群)が挙げられます。拘禁反応とは、刑務所の独房や精神科病院の隔離室に長時間閉じ込められたり縛られたりした結果、まるでふざけたように的外れな返事をするようになること(的はずれ応答)です。両方とも小さな子どものように振舞っており、一見奇妙な現象であると思われますが、この「困ったふり」という解離のメカニズムから説明することができます。
ちなみに、「困ったふり」は、前回(2025年9月号)でご説明した腰抜け(解離性神経学的症状症の脱力発作)と同じ生存戦略であると考えることができます。この起源の詳細については、以下の記事をご覧ください。
②合わせる心理―同調性

約300万年前以降、人類は部族集団を維持するために、周りとうまくやっていこうとする心理が進化しました(社会脳)。そのために、周りと同じような見た目や動きをすると、心地良くなるようになったでしょう。また、相手が強ければ従い、弱ければ従えていたでしょう。
2つ目は、周りに合わせる心理、同調性です。これは、先ほどの「困ったふり」で生き延びるのとは対照的に、「合わせるふり」で生き延びることです。
なお、この同調によって、従う心理が極端になってしまったのがストックホルム症候群とマインドコントロール、従える心理が極端になったのがモラルハラスメントです。ちなみに、ストックホルム症候群とマインドコントロールは、解離症のその他として分類されていますが、モラルハラスメントは解離症を含め精神障害には分類されていません。進化精神医学的に考えれば、ストックホルム症候群やマインドコントロールと相互作用するモラルハラスメントも同じく解離症に分類されても良さそうなのにです。そのわけは、モラルハラスメントを病気として認定してしまうと法的にある程度許容しなければならなくなるからです。いくら病的な要素があっても、病気認定をしてしまうと被害者感情を逆なでしたり、犯罪抑止の観点からは逆効果になる可能性があります。このようなことから病的な要素を考慮しない(考慮するべきではない?)という社会的な「事情」が影響していることがうかがえます。
ストックホルム症候群とモラルハラスメントの起源の詳細については、以下の記事をご覧ください。
ちなみに、いわゆる「こっくりさん遊び」も、集団で無意識に同じ答えを導いてしまうなどの一見奇妙な現象に思われます。また、いわゆる「後追い自殺」(ウェルテル効果)も、生物としての生存本能に反していて不自然に思われます。しかしこれらも、この「合わせるふり」という解離のメカニズムから説明することができます。



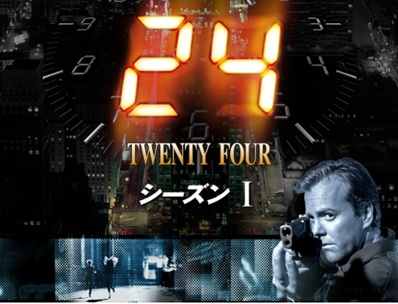

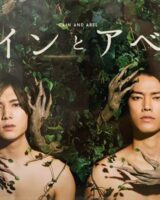
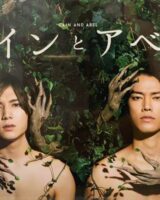

 ページトップへ
ページトップへ