【4ページ目】2025年5月号 記念日「多様な性にYESの日」【その1】なんで性は多様なの?-性スペクトラム

④性表現の起源-社会脳の進化
約700万年前に人類が誕生して、約300万年前に家族、その後に血縁でつながった部族をつくるようになりました。そして、男性たちは同性集団で狩りをして、女性たちは同性集団で子育てをするようになりました。これは、集団における性役割(性別役割分業)の起源です。この時、子どもは思春期になる頃、大人の同性集団に好意を持って迎え入れてもらえるように、男の子は男らしく、女の子は女らしくして、同性の大人のまねをしたでしょう。同時にこれは、同年代の異性への性的アピールになっていたでしょう。逆に言えば、異性のまねはしなくなるということです。これは、集団でうまくやっていくための能力(社会脳)の1つと言えます。
4つ目の段階は、性表現の起源、つまり社会脳の進化です。性表現とは、見た目や印象の性差を際立たせることで、集団としての生存戦略であり、個人としての生殖戦略であったというわけです。例えば、男性なら狩りの能力の高さをほのめかす筋肉質な体型やこだわり(システム化)の仕草であり、女性なら妊娠出産や子育ての能力の高さをほのめかすふくよかな体型や共感的な仕草です。なお、システム化と共感性の起源の詳細については、以下の記事をご覧ください。
やがて、約20万年前に言葉を話すようになってから、男性的な話し方、女性的な話し方の性差が生まれました。さらに、約7万年前に、服を着るようになってから、男性的な服装、女性的な服装の性差が生まれました。また、化粧が発明されてから、特に女性は化粧をして、性的にアピールするようになりました。こうして、男性はより男性らしく、女性はより女性らしく振舞うようになり、この性表現は文化的に固定化されるようになりました。
そんななか、現代、性自認が性別と同じで性的指向が異性のマジョリティであっても、性表現において同性ではなく異性の服を着たがる人が特に男性でいます。サブカルチャーでは、いわゆる 「女装家」「女装子(じょそこ)」「男の娘(おとこのこ)」などと呼ばれていますが、正式にはクロスドレッシングと呼ばれています。これも、本人たちが苦痛を感じている場合、異性装障害(DSM-5)と精神医学的に診断され、精神科治療の対象になります。
なお、この診断基準には、自分が女性になることへの性的な興奮(自己女性化性愛)の有無を特定する項目があり、将来的にトランスジェンダーになる可能性の高さが指摘されています(*1)。このことから、クロスドレッシングは、もともと性自認が中性(ジェンダーフルイド)寄りの人が無意識にも一時的にも異性になりきろうとする行動ととらえることができるでしょう。ちなみに、男性の自己女性化性愛とは対照的に、女性の自己男性化性愛も理屈としては存在するはずですが、臨床的にはまれであるため、診断基準には記載されていません。
つまり、原始の時代に性別役割分業をしていた人類において、その文化によって、性表現は男性と女性で連続的であることが分かります。これは、性表現における性スペクトラムと呼ぶことができるでしょう。






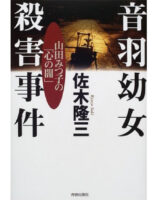
 ページトップへ
ページトップへ