【3ページ目】2025年5月号 記念日「多様な性にYESの日」【その1】なんで性は多様なの?-性スペクトラム

③性自認の起源―社会性の進化
約3億年前に哺乳類が誕生してから、単独行動ではなく群れ行動をする種が現れました。そして、近親相姦を回避するために、基本的に同性だけの群れになるように進化しました。例えば、リス(ベルディングジリス)は、大人になるとオスは親元を離れますが、メスは親元に残り、メスだけで血縁のある群れ(母系家族)をつくります。その後に誕生した真猿類もそうです。一方、チンパンジーは、大人になると逆にメスが親元を離れて他の群れに加わり、オスは親元に残り、オスたちだけで血縁のある群れ(父系家族)をつくります。
このように、同性で群れ行動をするためには、自分がどちらの性なのかの認識(性自認)をする必要があります。逆に、これができなければ、オスだけかメスだけかに偏った群れをつくることができません。
3つ目の段階は、性自認の起源、つまり同性の群れ行動のための社会性の進化です。性自認とはそもそも社会的なもので、個人のなかだけでは生まれません。性的指向が出生後に固定化されるのに対して、この性自認は大人になるまで(思春期)に遅れて発達して固定化されるようになります。
これは、子どもの心理発達の性差が根拠になります。実際に、小学校3、4年から、男の子は男の子同士で集まって対戦や冒険をして、女の子は女の子同士で噂話などのガールズトークを好むように、自然と同性同年代の集団をつくるようになります。この時期はギャングエイジと呼ばれています。
また、画像研究も根拠になります。実際に、性自認を司る脳部位(性自認中枢)は分界条床核(BSTc)であることが特定されており、これは男性ホルモンの影響を受けないことも確認されています(*5)。そして、特に思春期にその変化が確認できることも分かっています(*7)。
性自認中枢は男性ホルモンの影響を受けないことから、女性が胎児期に男性ホルモンを浴びて性的指向が変わっても、必ずしも性自認は変わらないことが分かります。実際に、先ほども触れたように、胎児期に男性ホルモンが出すぎた女性(先天性副腎過形成症)は性的指向が女性になる人は11%でしたが、そのなかで性自認が男性に変わる人は5%、変わらない人は11-5=6%いることになります。
つまり、胎児期の男性ホルモンの量の変化の影響を受けて性的指向が変わっても、性自認中枢が十分に働いていればシスジェンダーのままにとどまり、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルになります。しかし、性自認中枢が十分に働いていなければ、トランスジェンダーになり、同時に同性愛(※本人にとっては異性愛)や両性愛になります。逆に、性自認中枢が十分に働いていなくてトランスジェンダーになりながらも、胎児期の男性ホルモンの量の変化の影響がなければ、性的指向は変わらずに異性愛のまま(※本人にとっては同性愛)になる可能性が考えられます。
そして、性自認中枢が安定して働かないと、ジェンダーフルイドとなり、まったく働かないとノンバイナリーになる可能性が考えられます。
つまり、群れ行動をする哺乳類において、性自認中枢の機能によって、性自認はオスとメスで連続的であることが分かります。これは、性自認における性スペクトラムと呼ぶことができるでしょう。
なお、同性の群れ行動の詳細については、以下の記事をご覧ください。




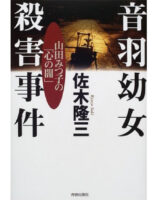

 ページトップへ
ページトップへ