【4ページ目】2025年4月号 海外番組「セサミストリート」【続編・その3】だから男性はこだわり女性は共感するんだ!だから人差し指の長さが違うんだ!―自閉症と情緒不安定性パーソナリティ障害の起源
なんで情緒不安定性パーソナリティ障害は幼児期に発症しないの?
 超男性脳の自閉症と超女性脳の情緒不安定性パーソナリティ障害は、共感性とシステム化の脳機能の極端な偏りとして対照的です。それなのに、なぜ自閉症は幼児期に発症するのに情緒不安定性パーソナリティ障害は思春期に発症するというタイムラグがあり、発症時期も対照的にはならないのでしょか?
超男性脳の自閉症と超女性脳の情緒不安定性パーソナリティ障害は、共感性とシステム化の脳機能の極端な偏りとして対照的です。それなのに、なぜ自閉症は幼児期に発症するのに情緒不安定性パーソナリティ障害は思春期に発症するというタイムラグがあり、発症時期も対照的にはならないのでしょか?
実際に、このタイムラグのために、現在の精神医学では、これら両者はそれぞれ発達障害とパーソナリティ障害というまったく別々の精神障害のカテゴリーに分類されてしまっています。
タイムラグが起きる答えは、情緒不安定性パーソナリティ障害は、共感性が高くなりすぎることで、自閉症のような不適応としてではなく、過剰適応として幼児期は潜在していると考えられるからです。つまり、幼児期に自閉症と同じようになんらかの変化は臨床的に確認できるということです。
例えば、以下です。
・親の顔色や体調の変化によく気づく。
・よく気が利いて、親の言うことをよく聞く。
・自分からお手伝いをする。
・親を喜ばせる振る舞いをする。
・嫌な思いをしても、我慢して取り繕う。
・めったに泣かず、手がかからない。
これらは、高すぎる共感性によって、観察力と演技力という潜在能力を発揮しています。これを一言で言えば、いわゆる「良い子」です。「良い子」は子育てするには楽で、親からは望ましいと思われがちです。「良い子」(過剰適応)の心理の詳細については、以下の記事をご覧ください。
しかし、ある状況で、「良い子」であることが裏目に出ます。
それは、虐待をはじめとするマルトリートメント(不適切なかかわり)です。「良い子」である分、親に十分に構ってもらえなくても、「良い子」であり続けようとします。そして、必死で親に構ってもらおうとして、構ってもらえるかどうかに敏感になります。その後、女性ホルモンの放出が高まる思春期に、交際相手に構ってもらえるかどうかにも敏感になり、「プレゼント」(構ってもらえること)を過剰に求めるようになるのです。
このような行動を駆り立てるのは、情緒不安定性パーソナリティ障害の中核症状である空虚感が当てはまります。よくよく考えれば、共感性が高いということは、その共感する相手がいなければいないほど当然空しさは増します。つまり、空虚感も、自閉症のこだわり(システム化)と同じように機能であるととらえ直すことができます。問題は、それが過剰であるということです。
例えば、相手にしがみついて、巻き込もうとします。これは、「死にたい」「死んでやる」など、いわゆる「死にたいアピール」として表現されます。さらに、これが行動化したのが自傷です。このような不適応を起こすことによって、情緒不安定性パーソナリティ障害はようやく顕在化するのです。
しかも、重度の場合は、共感性が高すぎる一方でシステム化が低すぎるために、周りに流されやすく、些細なことで傷つき、理屈が通じません。このような人が、占いなどのスピリチュアル系にハマりやすいのも納得が行くでしょう。
なお、傷つきやすさの心理の詳細については、以下の記事をご覧ください。
逆に言えば、自閉症をはじめとするシステム化の高い男の子は、良くも悪くも鈍く「良い子」になりません。そのため、構ってもらえないことに鈍感で、情緒不安定性パーソナリティ障害を発症しにくいとも言えます。
行動遺伝学の研究において、情緒不安定性パーソナリティ障害への家庭環境の違いの影響についての直接的なデータはまだ見当たりません。しかし、この病態の中核症状でもある「自殺念慮」については、遺伝12%、家庭環境11%、家庭外環境77%と算出され、家庭環境の違いの影響が出ています(*2)。家庭外環境の比率が大きいことから、実際の失恋(恋愛関係)やいじめ(友人関係)などの影響が大きいことも考えられます。
臨床的にも従来から、情緒不安定性パーソナリティ障害の要因として、マルトリートメント(家庭環境)が指摘されています(*3)。
逆に、自閉症においては、遺伝80%、家庭環境0%、家庭外環境20%という結果が出ており、家庭環境の違いの影響はありません。つまり、マルトリートメントによって自閉症になることはないことが分かります。


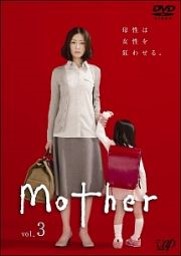
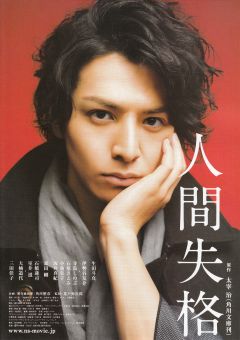


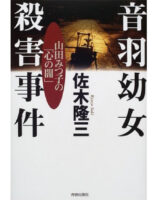
 ページトップへ
ページトップへ